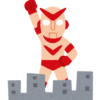目標(ゴール)を複数作る!?ハク流上手くいかなくても落ち込まい方法

仕事がうまくいかずに落ち込む。ダイエットにチャレンジしたけど上手くいかずに落ち込む。
落ち込んで周りに相談すると「お前はメンタルが弱い」と言われまた落ち込む。「じゃあどうしたら良いんだ!!」そう思った経験はないでしょうか?
今回はそんな人向けに落ち込みを減らす方法を今ご紹介していこうと思います。
Contents
どんな時に落ち込むか考えてみた。自身の経験から導き出した仮説
私は仕事をしている時に失敗したり上手く行かないとき、上司に怒られたときなどによく落ち込んでいました(今もそうですが)。
そんな時にふと「そもそも人はどんな時に気持ちが落ち込むのか?」について考えました。そうすると、物事がうまくいかないとき、目標を達成できなかったとき、失敗したときに自分は落ち込むことがわかりました。
それを突き詰めていくと、私は自分が勝手に思い描いた通りの結果にならない、思い描いたゴール(目標)に到達できないと落ち込んだりイライラしたりと負の感情が生まれるということがわかりました。
そしてこのことから「逆に自分が思い描いた通りの結果になる、思い描いたゴール(目標)に到達できれば気持ちが落ち込みにくいのではないか?」という仮説にたどり着きました。
自分が思い描いた通りの結果を得る、思い描いたゴール(目標)に行くためには設定する目標が大切
前の章の仮説から考えると、100%自分が思い描いた通りの結果、思い描いたゴール(目標)に到達できさえすれば、気持ちが落ち込むことはないはずですが、そんなことは可能なのでしょうか?
残念ながら、全部自分の頭が勝手に都合よく思い描いた通りに物事が進むことや、思い描いたゴールに行けることなんてそうそうあることではありません。
しかし一部だけなら自分が思い描いたとおりの結果を得ることや、思い描いたゴールに到達することも可能だと私は思っています。一部でも思い描いたとおりになれば落ち込みは少しかもしれませんが緩和します。
自己完結型の目標なら結果やゴールは自分の思いのまま
そもそもなんで自分が思い描いた通りの結果にならないのでしょうか?また思い描いたゴール(目標)に到達できないのでしょうか?それは物事が環境や他者の影響を大きく受けているからです。
例としては、「上司と良好な関係を築く」などの目標はこれに該当します。自分がどんなに頑張っても上司が私と良好な関係を築く気がなければこの目標を達成できません。これは「上司と良好な人間関係を築く」という目標が達成できるかは自分の努力だけで決まらずに他者の影響に左右されていると言えます。
目標には結果が他の影響によって変わるもの(ここでは「外部影響型」と呼びます)と自己完結するもの(ここでは自己完結型と呼びます)の2つがあります。
外部影響型は自分の努力だけでなく環境や他者の影響などによって目標を達成できるかが変わるものです。
一方、自己完結型は自分の努力や行動だけで目標を達成できるかかが決まるものです。
例として言えば「毎日に上司に元気よく挨拶する」という目標はこれに該当します。これは上司がどうであれ自分の行動次第で目標を達成できます。
自己完結型の目標なら思い描いたとおりになる=落ち込まい!!
話を戻しますが、小さな自己完結型の目標なら、100%自分が思い描いた通りの結果や思い描いたゴール(目標)を得ることができます。
それはつまり、気持ちが落ち込みにくいということです。
私の理屈はこのようなものです。
ゴチャゴチャ言ってますが、外部影響型と自己完結型の両方の目標を立てると落ち込みにくいよということを知っていただけたら幸いです。
自己完結型の目標だけではダメなのか?
ここまでの話を聞いて「自己完結型の目標だけではダメなのか?」という疑問を持つ方もいると思います。
それだけでも悪くないと思いますが、個人的には現実的ではないように感じており、外部影響型目標と自己完結型目標の両方を設定することがオススメです。その理由をここでは説明します。
理由1:物事の多くは外部影響型
小さな自己完結型の積み重ねが大きな物事の達成につながると思うので自己完結型の目標設定は非常に大切だと思います。しかし、何かある程度の大きさがある目標は基本的に外部影響型の目標です。
先程の説明したように「上司との人間関係を良くしたい」という目標も自分の努力だけでは解決することはできません。
ダイエットにしても同様です。これも外部影響型の目標です。遺伝的な要素もあるでしょうし、家族と同居しており食生活を自由に変えることができないということもあり自分の行動だけで結果が決まるものではありません。
このように一般的な目標は外部影響型が多いのです。
理由2:外部影響型目標に本当に望む結果やゴールがあるかもしれないから
外部影響型の目標は最初に書いた通り、私達の頭が勝手に思い描いたものです。しかしそこに自分自身の願望がこもっており、自分の求める最終的なゴールがあるかもしれないので、否定するのは良くないと思っています。
そしてそもそも、自己完結型の目標は外部影響型の目標と同じベクトル上にあり、基本的には外部影響型の目標を達成するために使われるスモールステップに近い位置づけです。
理由3:外部影響型目標は自分が勝手に作ってしまうから
仮に本当に外部影響型の目標が不要だとしても、勝手に作ってしまうことをわざわざ止めるというのは非常に難しいことだと思っています。
外部影響型の目標というものは価値観や認知などが複雑に絡み合ってできているものだと思うので、この勝手に作られる外部影響型を止めるということは難しいですし、わざわざ止めるのに時間や労力を費やす必要はないと考えています。
その結果として、自己完結型の目標だけということになりません。
理由3:自己完結型はスモールステップ。達成感は小さい
自己完結型の目標は基本的にスモールステップになることが多いように思います。例えば、朝活のために明日、いつもより早く会社に行くためにいつもより5分早く目覚ましをセットするという自己完結型の目標を立てたとしましょう。
それはそれで立派ですし自分を褒めれば良いと思います。しかし達成感はそこまで大きくなく、やはり本来の目標を達成したときに比べて達成感は小さいように感じます。
理由4:自己完結型目標は良くも悪くも自分の責任になる
自己完結型の目標はできる・できないが自分にかかっています。なのでできないと自分を責めてしまうことがあります。一方で外部影響型の目標は自分が行動をしなくても、外部の影響でうまくいくことがあります。自己完結型だけでなく外部影響型の目標も設定していくことでより上手くいくという結果を得やすくなります。
「なんか都合が良すぎるのではないか?」と疑問を持つ人がいるかも知れませんが、自分が行動するというのも結果を出すための手段の一つに過ぎませんし、必要以上に自分に厳しくしなくても良いでしょう。むしろ自己完結型の目標をできずに自分を責めてしまうタイプの人はこれくらい自分に甘くても大丈夫ではないでしょうか。
理由5:外部影響型と自己完結型を組み合わせる方がメンタルケアできる
上のような理由があるために私は外部影響型の目標をまず立てて、それに関係する自己完結型目標を立てるようにしています。そうすることで外部影響型の目標が達成できなかったときに「でも自分は自己完結型目標はちゃんと達成できた。やれることはやっている。努力している。今回は運がなかっただけ」と考えるようにし落ち込みを少し緩和しています。
具体的な方法と例
では具体的にはどのように外部影響型目標と自己完結型目標を組み合わせていけば良いのでしょうか?ここでは私の行っている具体的な方法と具体例を紹介していこうと思います。
具体的なやり方1(今ある目標に自己完結型目標を組み合わせる場合)
1.自分が今持っている目標や求めている結果が自己完結型が外部影響型かを考える
基本的には自己完結型の目標は「自分が~する」という形になります。そこに自分の行動以外の要素が関わる場合は全部外部影響型です。
外部影響型には運や才能も含まれます。
2.自分の外部影響型の目標のスモールステップとして自己完結型の目標を設定する。
これは多すぎなくて結構です。達成したらまた追加していけばよいです。
3.自己完結型の目標を達成したら褒める
これをすることでモチベーションを維持できますし、肯定感高まります。
4.外部影響の目標を達成できなかった場合も、自己完結型目標の達成に目を向ける
「自分は~という自己完結型の目標を達成できた。全部できなかったわけではない。思い通りになったこともあった。そのための努力はした。やれることはやった」と褒めると自分がダメだと落ち込んだり、物事が思い通りにいかないことばかりではないと思え少しイライラが減ります。
この他にも自分が何か作業などをする前に、経験上失敗したら落ち込みそうだなと思ったら、その作業に関して自己完結型の目標を設定していくと良いです。
私はこう使っています
私は人間関係や就職活動の際にこの方法を使っていました。
人間関係では「今、上司に話しかけると嫌な顔をされるかもしれない」と不安になることがよくありました。そして実際に嫌な顔をされたら必要以上に落ち込んだり気にしていました。
そこで私は話しかける前に自己完結型目標として「言いたいことを上司に声を掛ける前に整理する」「整理したものをただ上司に話す」を立てました。そして、実際に嫌な顔をされても「自分はちゃんと目標を達成できた。前に進んでいる。仕事で必要なことをしている。よくやった」と褒めるようにしました。
上司に嫌な顔をされないという外部影響型の目標は達成できなくても、自分の思い描いた結果を残せた部分が少しでもあると気分は多少ですがマシなものになります。
また就職活動では不採用の通知を受け取ると落ち込むのはわかっていたので、事前に自己完結型の目標を設定していました。それはその時々によって違いますが、「前回よりも書類はきれいに書く」とか「面接の時は絶対に笑顔を意識する」などを設定しました。
そうすることで、「不採用だったけど、得るものがあった」と思えて気持ちを切り替えやすくなりました。
視野を広げて気持ちを安定させよう
人間誰しも落ち込むことはありますし、絶対に落ち込まなくなるのは難しいかもしれません。しかしちょっとして工夫をするだけで、気持ちが楽なる。落ち込まなくて済むのなら良いのではない?
物事がうまくいかないと、視野が狭くなり自分の悪い点ばかりに目がむいしまいがちです。しかし実は頑張ってやってきたこと、褒めても良いことも沢山あるはずです。
今回ご紹介した方法を使って狭くなった視野を広げてみてください。気持ちが少しかもしれませんが楽になると思います。
この記事が少しでも誰かの役に立てば幸いです。